C-MAC youth
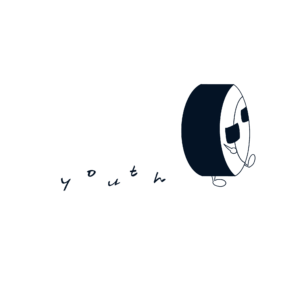
お問い合わせ・質問
C-MAC Youthでは MRI 初心者の皆様からの質問を募集しております。下記フォーマットよりお気軽にご質問ください♪
≫ 注意事項 ≪
- 頂いた質問は勉強会で紹介することがあります。
当月の勉強会テーマに即した質問を優先的に紹介いたします。時間の都合上勉強会で取り上げることができなかった質問は、当ホームページにて回答いたします。
- 内容によっては回答しかねる場合がございます。
こんなこと聞いたら恥ずかしいかな?他の研究会ではなかなか聞けない…といった、MRI 初心者の皆様からの質問を募集しております。C-MAC Youth への質問をぜひお待ちしております♪
Q&A
QUESTION AND ANSWER
たくさんのご質問ありがとうございます!
勉強会の時間内でお答えできなかった質問のお返事です。
第23回勉強会
「重度の側弯がある患者さんを撮影する際、矢状断の断面設定はどのようにしていますか?」
胸椎側弯症であれば、頂椎部の上下に分けて2回撮像を行っています。
スライス枚数を伸ばすこともあります。
側弯症患者には神経鞘腫等が生じる場合もあるため、Corを撮像します。
3DSE系シーケンス(CUBEやVISTA等)の使用もいいのかなと思います。
胸椎側弯症であれば、頂椎部の上下に分けて2回撮像を行っています。
スライス枚数を伸ばすこともあります。
側弯症患者には神経鞘腫等が生じる場合もあるため、Corを撮像します。
3DSE系シーケンス(CUBEやVISTA等)の使用もいいのかなと思います。

「Balanced SSFPの撮像断面はCorでしょうか?また、どういった場面で撮影しているのでしょうか?
」
Myeloを観察する場合には、Balanced SSFP系のCorを撮像します。
聖隷佐倉では、Axで撮像をしています。
医師の指示で撮像を行いますが、ヘルニアや腰椎症の患者に多く脊髄神経の走行をAx断面で確認しています。
術前検査時に多い印象です。
Myeloを観察する場合には、Balanced SSFP系のCorを撮像します。
聖隷佐倉では、Axで撮像をしています。
医師の指示で撮像を行いますが、ヘルニアや腰椎症の患者に多く脊髄神経の走行をAx断面で確認しています。
術前検査時に多い印象です。

「脊髄の信号変化が微妙な時、薄いスライスなどは用意されていますか?」
脊髄の信号変化が微妙であることを神経鞘腫等の腫瘍性病変と仮定した場合には、スライス間隔を薄くしています。
信号変化の際には、薄いスライスより多断面からの様々なシーケンスを撮像することが多いです。
また、早期急性期や亜急性期の活動性の低い脊髄炎に関しては、SCLEW(Spinal Cord Lesion Weighted Image)というシーケンスがSIGNA甲子園で報告されており、撮像している幹事施設もあります。
脊髄の信号変化が微妙であることを神経鞘腫等の腫瘍性病変と仮定した場合には、スライス間隔を薄くしています。
信号変化の際には、薄いスライスより多断面からの様々なシーケンスを撮像することが多いです。
また、早期急性期や亜急性期の活動性の低い脊髄炎に関しては、SCLEW(Spinal Cord Lesion Weighted Image)というシーケンスがSIGNA甲子園で報告されており、撮像している幹事施設もあります。

「脊椎転移でT1 Dixon法は、FSEとGREのどちらを選択されていますか?
コントラストが変化するとどこかで聞いたことがあったのですが。
」
医師の考え方による部分もあると思います。
医師によるとSE系 Dixon法の方がGRE系シーケンスよりもコントラストがわかりやすいとお話を聞いています。
医師の考え方による部分もあると思います。
医師によるとSE系 Dixon法の方がGRE系シーケンスよりもコントラストがわかりやすいとお話を聞いています。

「DWIのMPGの印加軸は各断面でどのように設定されていますか?」
GEでは、印加軸のかけ方をALL(3軸に印加)や3in1(3軸同時)・Tetraと選べるのですが、基本的に全ての断面でALL(3軸に印加)法を使用しています。
GEでは、印加軸のかけ方をALL(3軸に印加)や3in1(3軸同時)・Tetraと選べるのですが、基本的に全ての断面でALL(3軸に印加)法を使用しています。

「脊椎分離症の時は何を撮像されていますか?
」
聖隷佐倉では、T2 T1 STIR SagとAx、STIR Corを撮像しています。
近年では、FRACTUREなどのBone Imagingによる骨折線の描出やDESS(Double Echo Steady State)による骨髄浮腫の評価が有用との報告もあります。
聖隷佐倉では、T2 T1 STIR SagとAx、STIR Corを撮像しています。
近年では、FRACTUREなどのBone Imagingによる骨折線の描出やDESS(Double Echo Steady State)による骨髄浮腫の評価が有用との報告もあります。

「胸椎や腰椎でZ軸方向のFOVの限度はありますか?
広範囲の撮像要望が多く、感度ムラや磁場の不均一で画像が劣化します。
」
装置やメーカーにもよると思いますが(傾斜磁場強度等の違い)、聖隷佐倉の1.5T装置では、FOV36上限にしています。FOV40に設定すると画像の劣化が大きく生じます。
装置やメーカーにもよると思いますが(傾斜磁場強度等の違い)、聖隷佐倉の1.5T装置では、FOV36上限にしています。FOV40に設定すると画像の劣化が大きく生じます。

第16回勉強会
「Sequential Orderの時にFLASH bandが出やすくなるのは何故ですか?」
FLASH bandはアーチファクトの1つです。 原因は磁場の不均一やresonance offset角により生じる残留横磁化が影響しています。 縞目の間隔はTRが長くなると短くなりアーチファクトが増加して見えます。 対策として、TRの値を小さくする。局所シミングを行い磁場均一性を高める。などです。 ご質問のSequential Orderの件では、明確な回答がわからなかったので、メーカーに問い合わせをしました。その回答を一部引用させていただきます。
「“一般的にCentric OrderよりSequential Orderのほうで目立つ“のはFLASH系シーケンスのことを指し、実際の装置で起こりうるのは1980年代ころの話で、現在では技術進歩により本現象が起こることはありません。」
FLASH bandはアーチファクトの1つです。 原因は磁場の不均一やresonance offset角により生じる残留横磁化が影響しています。 縞目の間隔はTRが長くなると短くなりアーチファクトが増加して見えます。 対策として、TRの値を小さくする。局所シミングを行い磁場均一性を高める。などです。 ご質問のSequential Orderの件では、明確な回答がわからなかったので、メーカーに問い合わせをしました。その回答を一部引用させていただきます。
「“一般的にCentric OrderよりSequential Orderのほうで目立つ“のはFLASH系シーケンスのことを指し、実際の装置で起こりうるのは1980年代ころの話で、現在では技術進歩により本現象が起こることはありません。」

「View shareingの解説をお願いします。」
Keyhole Imagingとは、ダイナミック収集において、1相目(または最終相)においてリファレンススキャン(FullScan)をし、以降、低周波成分のデータのみを収集し、収集しなかった高周波成分データはリファレンススキャンのものを代用することで、撮像時間の短縮をおこなう方法です。
収集するデータの割合はパラメータで変化させることができます。 View sharingは上記Keyhole Imagingと組み合わせることで動脈のブラーリングや静脈信号の混入を防ぐ技術です。
1時相につき高周波成分を何%収集するか、収集した時相を統合する時間的方向を設定することで時間分解能を向上させることができます。
Keyhole Imagingとは、ダイナミック収集において、1相目(または最終相)においてリファレンススキャン(FullScan)をし、以降、低周波成分のデータのみを収集し、収集しなかった高周波成分データはリファレンススキャンのものを代用することで、撮像時間の短縮をおこなう方法です。
収集するデータの割合はパラメータで変化させることができます。 View sharingは上記Keyhole Imagingと組み合わせることで動脈のブラーリングや静脈信号の混入を防ぐ技術です。
1時相につき高周波成分を何%収集するか、収集した時相を統合する時間的方向を設定することで時間分解能を向上させることができます。

「最後のハーフスキャンの画像(TFE)でコントラストが変化した気がするのですが、ハーフスキャンを使用するとコントラストは変化するのでしょうか?」
勉強会中にコントラストは変化しないだろうと回答しましたが、誤回答であったので訂正させていただきます。パラメータ設定上はTE,TRともに変えていないため、上記の発言をしてしまいました。申し訳ございません。 今回提示した画像はTFEで撮像した画像でした。位相方向にハーフスキャンを用いた場合、収集する位相エンコード数が減少いたします。そのためk-spaceへの充填数(TFE shot数)が変化することでコントラストに変化を生じました。また、脂肪抑制にSPAIRを用いていたのですが、これもハーフスキャンを入れるとSPAIRのInversion delayが変化するため脂肪抑制のかかり方も変化してしまうようです。 したがって、TFEでの撮像において、ハーフスキャンを使用するとコントラストに変化を生じてしまいます。
勉強会中にコントラストは変化しないだろうと回答しましたが、誤回答であったので訂正させていただきます。パラメータ設定上はTE,TRともに変えていないため、上記の発言をしてしまいました。申し訳ございません。 今回提示した画像はTFEで撮像した画像でした。位相方向にハーフスキャンを用いた場合、収集する位相エンコード数が減少いたします。そのためk-spaceへの充填数(TFE shot数)が変化することでコントラストに変化を生じました。また、脂肪抑制にSPAIRを用いていたのですが、これもハーフスキャンを入れるとSPAIRのInversion delayが変化するため脂肪抑制のかかり方も変化してしまうようです。 したがって、TFEでの撮像において、ハーフスキャンを使用するとコントラストに変化を生じてしまいます。

第14回勉強会
「プロペラで撮像する際にETLを変更すると幅も変わるのはなぜですか?」
PROPELLERはk空間の中心、すなわち位相エンコード方向と周波数エンコード方向の 周波数が0のところを回転中心としてデータ充填の軌跡が回転する撮像法です。
この方法では励起ごとに収集されるデータに周波数(0,0)のデータが必ず存在します。
信号強度の高い低周波成分のデータが信号強度の低い高周波成分のデータより密に収集されるので、周波数(0,0)のデータが最も多く収集されます。
ETLを増やした結果PROPELLERの幅が厚くなるのは、その分収集データ量が増えていると考えられます。
PROPELLERはk空間の中心、すなわち位相エンコード方向と周波数エンコード方向の 周波数が0のところを回転中心としてデータ充填の軌跡が回転する撮像法です。
この方法では励起ごとに収集されるデータに周波数(0,0)のデータが必ず存在します。
信号強度の高い低周波成分のデータが信号強度の低い高周波成分のデータより密に収集されるので、周波数(0,0)のデータが最も多く収集されます。
ETLを増やした結果PROPELLERの幅が厚くなるのは、その分収集データ量が増えていると考えられます。

「3D画像でのETLで100以上に設定されていることがあるのですが、これはどのように考えれば良いでしょうか。」
3Dの場合、直交する3軸に位相エンコーディングしてデータを収集しています。
2DのETLに加えて、もう一軸分の位相エンコード数も含まれるため、ETLの数が大きくなります。
当院の3T SIEMENSで例えると、設定時ETLを入力すると、「Echo Train Duration」が増減します。
こちらがコントラストの選択に重要な値で、例えばMRCPの際には800~1000辺り。
T1強調画像を取得するためには短く100~200程度に設定しております。
3Dの場合、直交する3軸に位相エンコーディングしてデータを収集しています。
2DのETLに加えて、もう一軸分の位相エンコード数も含まれるため、ETLの数が大きくなります。
当院の3T SIEMENSで例えると、設定時ETLを入力すると、「Echo Train Duration」が増減します。
こちらがコントラストの選択に重要な値で、例えばMRCPの際には800~1000辺り。
T1強調画像を取得するためには短く100~200程度に設定しております。

第11回勉強会
「シングルショットの時にTRがコントラストに関係ないのはなぜですか?」
シングルショット高速スピンエコー法は一度の励起で1スライスのk-space全ての信号を取得します。そのため同一スライスで2回目の励起パルスの出番は無く、TRが存在しません。
組織間の縦緩和の差が無い(完全に回復している)状態から励起パルスが照射されるため、TRは「∞」と表現されることもあります。
しかし多くの装置でシングルショット高速スピンエコー法の場合でもTRのパラメータが存在します。これはあるスライスの励起パルスから次のスライスの励起パルスまでの時間を表すことが多いです。
励起パルスはスライス選択性に照射されるため、TR後の励起パルスでは次のスライスしか励起されず、同一スライスでのT1緩和の制御はされません。そのため理論的にはコントラストに影響の無いものと考えられます。
よってこのTRは取り得る最短に設定するのが一般的です。
しかし実際はスライス間の距離やRFパルスの選択性によってはクロストークアーチファクトの影響、また別スライスのRFパルスによるMT効果の影響によってこのTRがコントラストに影響を与える場合があります。
シングルショット高速スピンエコー法は一度の励起で1スライスのk-space全ての信号を取得します。そのため同一スライスで2回目の励起パルスの出番は無く、TRが存在しません。
組織間の縦緩和の差が無い(完全に回復している)状態から励起パルスが照射されるため、TRは「∞」と表現されることもあります。
しかし多くの装置でシングルショット高速スピンエコー法の場合でもTRのパラメータが存在します。これはあるスライスの励起パルスから次のスライスの励起パルスまでの時間を表すことが多いです。
励起パルスはスライス選択性に照射されるため、TR後の励起パルスでは次のスライスしか励起されず、同一スライスでのT1緩和の制御はされません。そのため理論的にはコントラストに影響の無いものと考えられます。
よってこのTRは取り得る最短に設定するのが一般的です。
しかし実際はスライス間の距離やRFパルスの選択性によってはクロストークアーチファクトの影響、また別スライスのRFパルスによるMT効果の影響によってこのTRがコントラストに影響を与える場合があります。

「シングルショットだとTR=10000msでも500msでもコントラストは変わらずT2強調になる認識でよろしいでしょうか?またこの際はSARもほぼ影響しないということでしょうか?」
シングルショット高速スピンエコー法の場合、理論的にRFパルスのスライス選択性が完璧でオフレゾナンスパルスの影響が無いと仮定すると、設定TRは縦緩和に影響が無いため、設定TRに依存せずコントラストが決まります。
そのためどちらも同様なT2WIが得られます。
しかし実際にはTRが短いほど、クロストークやMT効果の影響によってコントラストが変化したり、局所的な低信号化や信号ムラが多少出たりします。
そのため可能であればTRを少し延長させると改善することがあります。
SARはスライス断面を限定せず、照射されるRFパルス全てを考える必要があります。
そのため、スライス間のTRだとしても、短くなればRFが時間軸で密になるためSARが大きくなります。
シングルショット高速スピンエコー法の場合、理論的にRFパルスのスライス選択性が完璧でオフレゾナンスパルスの影響が無いと仮定すると、設定TRは縦緩和に影響が無いため、設定TRに依存せずコントラストが決まります。
そのためどちらも同様なT2WIが得られます。
しかし実際にはTRが短いほど、クロストークやMT効果の影響によってコントラストが変化したり、局所的な低信号化や信号ムラが多少出たりします。
そのため可能であればTRを少し延長させると改善することがあります。
SARはスライス断面を限定せず、照射されるRFパルス全てを考える必要があります。
そのため、スライス間のTRだとしても、短くなればRFが時間軸で密になるためSARが大きくなります。

「大腿から膝をAX撮像する場合、スライス厚をどれくらいに設定しますか?また時間短縮方法を教えてください。」
JMRTSのホームページによると、大腿の撮像条件はスライス厚8mm、スライス間隔2mm程度で40枚にすることが推奨されています。
体型や検査目的により適宜調整する場面もあると思いますので、今回の内容を踏まえて検討していただければと思います。
時間短縮方法については下肢撮像に特徴的なものではありませんが、パラレルイメージングの併用が有効的です。
JMRTSのホームページによると、大腿の撮像条件はスライス厚8mm、スライス間隔2mm程度で40枚にすることが推奨されています。
体型や検査目的により適宜調整する場面もあると思いますので、今回の内容を踏まえて検討していただければと思います。
時間短縮方法については下肢撮像に特徴的なものではありませんが、パラレルイメージングの併用が有効的です。

「DWIのTRはどのように設定されていますか?」
JMRTSのホームページによると、DWIのTR設定に関して頭部では3000ms以上、上腹部では呼吸同期で1200ms~1600ms程度、後腹膜腔では4000~5000ms程度が推奨されています。
短いTRを用いることで撮像時間を短縮できますが、過度に短いTRはSNRやコントラストに悪影響を与える可能性があります。
JMRTSのホームページによると、DWIのTR設定に関して頭部では3000ms以上、上腹部では呼吸同期で1200ms~1600ms程度、後腹膜腔では4000~5000ms程度が推奨されています。
短いTRを用いることで撮像時間を短縮できますが、過度に短いTRはSNRやコントラストに悪影響を与える可能性があります。

「3T装置ではT1WI撮像時2回まわしで撮像しないといけないと聞いたことがありまして、ご教示いただけるとありがたいです。」
3T装置におけるT1WI撮像時の2回まわしは、SNR向上やコントラストを確保する目的で行われます。
しかし、撮像時間や患者負担を重視する場合は、1回まわしで撮像する場合もあります。
SNRを優先させるか、撮像時間を優先させるか、適切に判断し最適な撮像条件を選択することが重要です。
3T装置におけるT1WI撮像時の2回まわしは、SNR向上やコントラストを確保する目的で行われます。
しかし、撮像時間や患者負担を重視する場合は、1回まわしで撮像する場合もあります。
SNRを優先させるか、撮像時間を優先させるか、適切に判断し最適な撮像条件を選択することが重要です。

「Null pointの設定には計算式などを利用していますでしょうか?簡易的な考え方などあれば教えていただきたいです。」
Null pointはT1値を用いて計算する方法(T1値×0.693)のほか、撮像パラメータの調整によっても設定されることがあります。
今回の内容にもありましたが、TRの変動によりNull pointは変化してしまうため注意が必要です。
簡易的な考え方という点ではお答えが難しいですが、府中病院様のホームページにてnull pointの自動計算サイトが掲載されておりましたのでご紹介いたします。
https://seichokai.jp/fuchu/null_point/
実際に検査中に計算することは時間的にも難しいと思いますので、プロトコルの検討時などに使用することで、経験的なアプローチができるようになるかもしれません。
Null pointはT1値を用いて計算する方法(T1値×0.693)のほか、撮像パラメータの調整によっても設定されることがあります。
今回の内容にもありましたが、TRの変動によりNull pointは変化してしまうため注意が必要です。
簡易的な考え方という点ではお答えが難しいですが、府中病院様のホームページにてnull pointの自動計算サイトが掲載されておりましたのでご紹介いたします。
https://seichokai.jp/fuchu/null_point/
実際に検査中に計算することは時間的にも難しいと思いますので、プロトコルの検討時などに使用することで、経験的なアプローチができるようになるかもしれません。

「造影時にスライスを増やそうと思って2回回しにすると時相が微妙に変わってしまうと思いますがダイナミックでなければ問題ないでしょうか?」
撮像時のスライス増加に伴う時相変化に関しては、ダイナミック撮像でなければ通常問題ないと考えます。
ただし時相変化が大きくなると、解析の精度が低下する可能性があるため、適切な撮像パラメータの選択や撮像計画が重要です。
撮像時のスライス増加に伴う時相変化に関しては、ダイナミック撮像でなければ通常問題ないと考えます。
ただし時相変化が大きくなると、解析の精度が低下する可能性があるため、適切な撮像パラメータの選択や撮像計画が重要です。

「T2WIで推奨よりTRが長くなる場合、問題はありますか?」
T2WIで推奨よりTRが長くなる場合、通常問題ありませんが、撮像時間が長くなり、検査時の負担が増すことが考えられます。
最適なTRを選択することで、適切なコントラストと撮像時間のバランスを実現できます。
T2WIで推奨よりTRが長くなる場合、通常問題ありませんが、撮像時間が長くなり、検査時の負担が増すことが考えられます。
最適なTRを選択することで、適切なコントラストと撮像時間のバランスを実現できます。

「当院では四肢のT1WI撮像時2回まわしのシーケンスが多いのですが、TRがコントラストの担保できる範囲であれば1回まわしに変更するのは問題ありませんか?」
四肢のT1WI撮像時に2回まわしのシーケンスを1回まわしに変更する場合、TRがコントラストを担保できる範囲であればT1WIとして問題ありません。
1回まわしにすることで撮像時間の短縮や検査時の負担軽減が図れます。
TRによっては撮像できる最大枚数が変動しますが、こちらも検査目的範囲を適切に含めることができていれば問題ないと考えます。
ただしデフォルトのシーケンスに2回まわしが多いということは、ルーチン構築時にそうすべきとされた理由があったからだと考えられますので、ご施設として理由を確認した上でご検討されるとよいかもしれません。
四肢のT1WI撮像時に2回まわしのシーケンスを1回まわしに変更する場合、TRがコントラストを担保できる範囲であればT1WIとして問題ありません。
1回まわしにすることで撮像時間の短縮や検査時の負担軽減が図れます。
TRによっては撮像できる最大枚数が変動しますが、こちらも検査目的範囲を適切に含めることができていれば問題ないと考えます。
ただしデフォルトのシーケンスに2回まわしが多いということは、ルーチン構築時にそうすべきとされた理由があったからだと考えられますので、ご施設として理由を確認した上でご検討されるとよいかもしれません。

第10回勉強会
「中足骨の撮像はどうしていますか?」
発表担当者の施設での例をご紹介します。
位置決め画像撮像後、目的部位(足趾側か足底か)に応じた修正位置決め画像を撮像します。
3方向ともに中足骨が確認できたところで本撮像にうつります。
中足骨を横断像で1断面に収めるのは困難なため、目的部位がわかっている、もしくはSTIRなどで炎症部位が特定できれば、目的の足趾が広く描出できるようなスライス面に設定します。
発表担当者の施設での例をご紹介します。
位置決め画像撮像後、目的部位(足趾側か足底か)に応じた修正位置決め画像を撮像します。
3方向ともに中足骨が確認できたところで本撮像にうつります。
中足骨を横断像で1断面に収めるのは困難なため、目的部位がわかっている、もしくはSTIRなどで炎症部位が特定できれば、目的の足趾が広く描出できるようなスライス面に設定します。

「リウマチの患者さんの両手を撮像するときも両手挙上ですか。」
手下げで撮る場合の例をご紹介します。
この場合は両大腿に手をのせ、その上にコイルを置いて固定します。
上腕の下にタオルを敷いて、上からバンド固定することで、腕が疲れません。
上半身も少しあげておくと楽な様です。
手台を自作して大腿の上に設置するという方法もあり、多くの施設で工夫して撮像されております。
次にうつぶせで撮る場合の例をご紹介します。
この場合は乳腺検査用のコイル台を用いることで、呼吸が楽な状態で両手挙上のうつ伏せ姿勢をとることができます。
お持ちのコイルやアイテムの問題、また準備にかかる手間や時間制限もありますので、主治医や放射線科医とも相談しながら検討できるとよいと思います。
手下げで撮る場合の例をご紹介します。
この場合は両大腿に手をのせ、その上にコイルを置いて固定します。
上腕の下にタオルを敷いて、上からバンド固定することで、腕が疲れません。
上半身も少しあげておくと楽な様です。
手台を自作して大腿の上に設置するという方法もあり、多くの施設で工夫して撮像されております。
次にうつぶせで撮る場合の例をご紹介します。
この場合は乳腺検査用のコイル台を用いることで、呼吸が楽な状態で両手挙上のうつ伏せ姿勢をとることができます。
お持ちのコイルやアイテムの問題、また準備にかかる手間や時間制限もありますので、主治医や放射線科医とも相談しながら検討できるとよいと思います。

「創外固定をしている患者さんの撮像はどうしていますか。」
創外固定された患者さんを撮像している施設はyouth内では少なく、ポジショニングの紹介はできません。
医師側も金属という認識でオーダーされないのかもしれません。
固定具に関してはASTM規格に従い、各メーカーが「MR safe」から「MR conditional」に変更しているようです。
撮像条件の制限や監視が必要で、フレームをガントリー内に入れての撮像は要相談となるかと思います。
創外固定された患者さんを撮像している施設はyouth内では少なく、ポジショニングの紹介はできません。
医師側も金属という認識でオーダーされないのかもしれません。
固定具に関してはASTM規格に従い、各メーカーが「MR safe」から「MR conditional」に変更しているようです。
撮像条件の制限や監視が必要で、フレームをガントリー内に入れての撮像は要相談となるかと思います。

第5回勉強会
「造影前FLAIRのTI値と造影後FLAIRのTI値は変わりますか?」
FLAIRはCSFの信号を抑制したT2WIです。
造影剤は基本的にCSFに分布しないため、CSFを落とすという意味において造影前と造影後ではTI値を変える必要はないと考えます。
FLAIRはCSFの信号を抑制したT2WIです。
造影剤は基本的にCSFに分布しないため、CSFを落とすという意味において造影前と造影後ではTI値を変える必要はないと考えます。

「救急で頭部撮影を行う場合T2WIは撮るべきでしょうか。現在当院ではDWI FLAIR MRAで運用しています。」
必要ないと考えます。
脳梗塞がいつ発症したのか、DWI+T2WIの信号パターンによって評価しますが、FLAIRがCSFを抑制したT2WIに、DWIの原画像がT2WIとなり、FLAIRを撮影していればその評価が可能になります(DWI-FLAIR mismatch)。
そのため、T2WI追加するより、トータル撮像時間を短くした方が救急の場面では有用だと考えます。
必要ないと考えます。
脳梗塞がいつ発症したのか、DWI+T2WIの信号パターンによって評価しますが、FLAIRがCSFを抑制したT2WIに、DWIの原画像がT2WIとなり、FLAIRを撮影していればその評価が可能になります(DWI-FLAIR mismatch)。
そのため、T2WI追加するより、トータル撮像時間を短くした方が救急の場面では有用だと考えます。

「3T頭部のTIWIでコントラストつけるためにIRパルスを印加すると思うのですが、その場合のTRの適切な値はどのくらいなのでしょうか?」
SIR-SE∝[1-2e(-TI/T1)+e-(TR-TElast)/T1]がT1に影響を与える式となります。
TEを最小に設定し、CSF(3Tで4000ms)のT1値を代入して0になるTI/TRが最適なTRとなります。
また、中枢神経組織コントラストはTR2000ms、TI862msの組み合わせで最も高くなると報告されています。
参考文献:MR of the spine with a fast T1-weighted fluid-attenuated inversion recovery sequence
SIR-SE∝[1-2e(-TI/T1)+e-(TR-TElast)/T1]がT1に影響を与える式となります。
TEを最小に設定し、CSF(3Tで4000ms)のT1値を代入して0になるTI/TRが最適なTRとなります。
また、中枢神経組織コントラストはTR2000ms、TI862msの組み合わせで最も高くなると報告されています。
参考文献:MR of the spine with a fast T1-weighted fluid-attenuated inversion recovery sequence

第4回勉強会
「髄膜炎などで造影後にFLAIRを撮像することはありますか? 初心者でいまいち原理がわからないので教えていただきたいです。
」
ご質問の通り髄膜炎では造影後にFLAIRが有用なことがあります。
その原理としていくつか理由がありますので、ご紹介します。
①(造影前でもそうですが)FLAIRではCSFが無信号のため、隣接する髄膜・脳神経・皮質病変が目立つため。
②FLAIRはTR・TEともに長いので、基本的にはT2強調画像のコントラストです。T2強調像なのになぜ造影効果があるの?と不思議に思われるかもしれませんね。ポイントは髄膜炎の造影剤濃度に関係しています。 T1が長いような個所(病変部は基本的に正常より長い)に造影効果が生じると、縦磁化は一気に回復します。今回の勉強会の内容にもありましたが、T2強調ではT1強調よりもT2短縮の影響を受けやすいので、造影剤が”高濃度”であればT2減衰の影響を強く受けて信号強度は低下します。 一方で髄膜炎は造影剤で染まりますが、それほど”高濃度”ではないという文献があります。このように造影剤が”陽性効果優位な程度に低濃度”であるため、T2減衰はそれほど起こらず、信号強度は高信号となると考えられています。
③血管内は造影剤が高濃度となるので、造影FLAIRでは高信号にならず、脳表と正常血管との区別がつきやすいため。
④FSE-FLAIRではMT効果によって脳実質が信号が低下するので、造影効果で信号増強された病変とコントラストが付きやすいため。
ご質問の通り髄膜炎では造影後にFLAIRが有用なことがあります。
その原理としていくつか理由がありますので、ご紹介します。
①(造影前でもそうですが)FLAIRではCSFが無信号のため、隣接する髄膜・脳神経・皮質病変が目立つため。
②FLAIRはTR・TEともに長いので、基本的にはT2強調画像のコントラストです。T2強調像なのになぜ造影効果があるの?と不思議に思われるかもしれませんね。ポイントは髄膜炎の造影剤濃度に関係しています。 T1が長いような個所(病変部は基本的に正常より長い)に造影効果が生じると、縦磁化は一気に回復します。今回の勉強会の内容にもありましたが、T2強調ではT1強調よりもT2短縮の影響を受けやすいので、造影剤が”高濃度”であればT2減衰の影響を強く受けて信号強度は低下します。 一方で髄膜炎は造影剤で染まりますが、それほど”高濃度”ではないという文献があります。このように造影剤が”陽性効果優位な程度に低濃度”であるため、T2減衰はそれほど起こらず、信号強度は高信号となると考えられています。
③血管内は造影剤が高濃度となるので、造影FLAIRでは高信号にならず、脳表と正常血管との区別がつきやすいため。
④FSE-FLAIRではMT効果によって脳実質が信号が低下するので、造影効果で信号増強された病変とコントラストが付きやすいため。

「アダムキュービッツを描出する際に、秒4くらいの速度で注入した経験があるのですが、高速で注入しすぎると造影剤の信号がT2短縮効果の影響で低信号になる恐れもありますでしょうか?
」
大動脈瘤・大動脈解離診断ガイドラインではtime-resolved MRAが推奨されています。この方法では造影剤を3~4mL/s程度の速度で急速静注しながら高速撮像で1回あたり10秒程度の撮像時間で同じ場所を繰り返し撮像します。MRIでの診断能は69~84%と言われています。他には0.2mL/sで低速静注しながら撮像する方法もあるそうです。
大動脈瘤・大動脈解離診断ガイドラインではtime-resolved MRAが推奨されています。この方法では造影剤を3~4mL/s程度の速度で急速静注しながら高速撮像で1回あたり10秒程度の撮像時間で同じ場所を繰り返し撮像します。MRIでの診断能は69~84%と言われています。他には0.2mL/sで低速静注しながら撮像する方法もあるそうです。

「尿管腫瘍疑いで造影MRIが依頼された場合、プロトコルはどうされていますか?撮像シーケンス、造影剤量や撮像タイミングなどを教えてもらいたいです。」
回答者の施設では目的によって造影剤量は変えていません。(以前は腎・尿管系は造影剤量半量にしていたそうですが造影効果が薄いことがあるとのことで通常量になったそうです) 尿管腫瘍は造影CTの診断能が優れるため特別な理由がないためMRIでスクリーニングを行うことはありませが、回答者が確認した範囲ではT2、fsT2、DWI、T1等の一般的な腹部のシーケンスに加えてMRUの撮像とMIP像の作成で検査を行っています。MRUは単純で撮像しており造影検査は行っておりません。 勉強会の指定教科書の「MRI自由自在」では、腎系は造影剤半量、urographyでは1/5程度とされています。
回答者の施設では目的によって造影剤量は変えていません。(以前は腎・尿管系は造影剤量半量にしていたそうですが造影効果が薄いことがあるとのことで通常量になったそうです) 尿管腫瘍は造影CTの診断能が優れるため特別な理由がないためMRIでスクリーニングを行うことはありませが、回答者が確認した範囲ではT2、fsT2、DWI、T1等の一般的な腹部のシーケンスに加えてMRUの撮像とMIP像の作成で検査を行っています。MRUは単純で撮像しており造影検査は行っておりません。 勉強会の指定教科書の「MRI自由自在」では、腎系は造影剤半量、urographyでは1/5程度とされています。

「造影後のT1WI脂肪抑制併用撮像時、chess法を用いずにGRE系のopposed phase(TE2.3ms付近)で撮像するのはありでしょうか?
やはり、chess法やSPAIR等を併用した方が良いのでしょうか?
教えてください。」
当日の回答では頭部に関しての質問と勘違いしてしまい趣旨と異なる回答をしてしまいましたが、他の部位だと磁場の不均一を考えてoppで撮像することもあります。その場合“paradoxical suppression”の影響も考慮しなくてはいけません。 パネリストの経験談ですがoppのほうが造影効果を確認しやすいこともあるそうです。
paradoxical suppressionとは:
造影後opp phase画像で造影前よりも信号が低下する現象。oppではpixcel内の水(Mw)と脂肪(Mf)の差分の絶対値 |Mw - Mf| が信号強度になります。pixcel内に多くの脂肪と少しの水が混在していたとして造影すると水の信号が増強されて脂肪との差が少なくなり結果として信号強度が低下する。 (例)造影前 Mw 1 Mf 9 |1 - 9|=8 造影後 Mw 6 Mf 9 |6 - 9|=3
当日の回答では頭部に関しての質問と勘違いしてしまい趣旨と異なる回答をしてしまいましたが、他の部位だと磁場の不均一を考えてoppで撮像することもあります。その場合“paradoxical suppression”の影響も考慮しなくてはいけません。 パネリストの経験談ですがoppのほうが造影効果を確認しやすいこともあるそうです。
paradoxical suppressionとは:
造影後opp phase画像で造影前よりも信号が低下する現象。oppではpixcel内の水(Mw)と脂肪(Mf)の差分の絶対値 |Mw - Mf| が信号強度になります。pixcel内に多くの脂肪と少しの水が混在していたとして造影すると水の信号が増強されて脂肪との差が少なくなり結果として信号強度が低下する。 (例)造影前 Mw 1 Mf 9 |1 - 9|=8 造影後 Mw 6 Mf 9 |6 - 9|=3

第2回勉強会
「T2強調画像について、どこの部位だと TR 2000 で撮像できますか?」
臨床においての、SE(Spin Echo)法のT2強調画像のTRの設定値を調べました。
多くの教科書や参考書にはT2強調画像はTR=2000~4000msと記載があります。
上腹部など呼吸同期やSingle shotで息止め撮像する場合、その他MRCPでHeavyT2を撮像する際などは1000~2000、その他の設定条件により1000以下の設定にする必要があります。
その他、現場で使用するFSE法はTRを3000ms以上に設定していることが多く、特に前立腺や婦人科系はその値を大きくとっております。
混在する成分のT1を強調しないため、十分なTRが必要だからです。
時間との兼ね合いで可能な範囲で短くとお伝えしましたが、3000ms以上、部位によっては4000ms以上に設定する必要がありますので、各施設でご確認ください。
以下は磁気共鳴学会の推奨プロトコルに記載されていたTRです。
頭部4000ms以上
頚部3000~6000ms
脊椎3000~4000ms
前立腺4000~6000ms
婦人科系4000~7000ms
臨床においての、SE(Spin Echo)法のT2強調画像のTRの設定値を調べました。
多くの教科書や参考書にはT2強調画像はTR=2000~4000msと記載があります。
上腹部など呼吸同期やSingle shotで息止め撮像する場合、その他MRCPでHeavyT2を撮像する際などは1000~2000、その他の設定条件により1000以下の設定にする必要があります。
その他、現場で使用するFSE法はTRを3000ms以上に設定していることが多く、特に前立腺や婦人科系はその値を大きくとっております。
混在する成分のT1を強調しないため、十分なTRが必要だからです。
時間との兼ね合いで可能な範囲で短くとお伝えしましたが、3000ms以上、部位によっては4000ms以上に設定する必要がありますので、各施設でご確認ください。
以下は磁気共鳴学会の推奨プロトコルに記載されていたTRです。
頭部4000ms以上
頚部3000~6000ms
脊椎3000~4000ms
前立腺4000~6000ms
婦人科系4000~7000ms

「TR に関してですが、DWI を撮像する場合は TR 8000 で1acq で撮るのと、TR
4000 で2acq で撮るならどちらがいいのでしょうか?」
過去の文献でTRの変化に対するDWI像のSNRとコントラスト比の変化をまとめているものがありました。
どちらもTRを上げるほど高い値になりますが、6000ms程度でプラトーとなりました。
ご質問の2択では撮像時間の差も少ないですから 、理論上TR 80001acqの方が良いと思います。
ただ、TRは大きければ大きいほど良いというわけではないようです。
T2 Shine Throughの影響を考慮しなければならないため、妥当なラインでは目的組織やその周囲のT1値の2倍くらいのTRと言われているそうです。
また、クロストークが原因で、再構成像に階段状のアーチファクトが発生することがあります。
このような場合には分割で撮像することで影響が軽減されるという報告例もありますので、神経をターゲットとした際などには参考にしてみてください。
参考文献 「拡散強調画像におけるTRの変化とShine Through影響に関する基礎検討」日本放射線技術学会東北支部雑誌(Web) (Tohoku Journal of Radiological Technology (Web) 2018)
過去の文献でTRの変化に対するDWI像のSNRとコントラスト比の変化をまとめているものがありました。
どちらもTRを上げるほど高い値になりますが、6000ms程度でプラトーとなりました。
ご質問の2択では撮像時間の差も少ないですから 、理論上TR 80001acqの方が良いと思います。
ただ、TRは大きければ大きいほど良いというわけではないようです。
T2 Shine Throughの影響を考慮しなければならないため、妥当なラインでは目的組織やその周囲のT1値の2倍くらいのTRと言われているそうです。
また、クロストークが原因で、再構成像に階段状のアーチファクトが発生することがあります。
このような場合には分割で撮像することで影響が軽減されるという報告例もありますので、神経をターゲットとした際などには参考にしてみてください。
参考文献 「拡散強調画像におけるTRの変化とShine Through影響に関する基礎検討」日本放射線技術学会東北支部雑誌(Web) (Tohoku Journal of Radiological Technology (Web) 2018)

第1回勉強会
「膝の撮像でT2WIではなくてT2*WIを用いることがあるのはなぜでしょうか?」
T2WIでは筋肉、腱、軟骨などのコントラストが付きにくいですが、GRE法であるT2*WIでは脂肪組織の信号が減衰し、これらのコントラストが良くなるためだと考えます。
(筋肉:中程度信号、腱:低信号、軟骨:弱高信号)
ただしT2*WIの欠点もあります。
①GRE系シーケンスなのでアーチファクトが出る
②偽陽性が多い(整形外科医に確認しました)
以上の理由から、当院ではPdWI(プロトン密度強調像)を撮像しています。
通常のPdWIではT2減衰の影響をなるべく避けたいので、TEを最短(10~20ms)に設定するのが望ましいですが、膝関節では軟骨と周辺組織のコントラストをつけたいので、TEを通常よりも少し長め(30ms程度)に設定しています。
PdWIなのでSNも良く、アーチファクトも比較的少ないので採用されています。
また、軟骨イメージングでは基本脂肪抑制を用いて、軟骨の信号を持ち上げて診断を行いますので、FS PdWIの撮像も行っています。
結局はDrの好みになりますので、一つの意見として聞いていただければと思います。
T2WIでは筋肉、腱、軟骨などのコントラストが付きにくいですが、GRE法であるT2*WIでは脂肪組織の信号が減衰し、これらのコントラストが良くなるためだと考えます。
(筋肉:中程度信号、腱:低信号、軟骨:弱高信号)
ただしT2*WIの欠点もあります。
①GRE系シーケンスなのでアーチファクトが出る
②偽陽性が多い(整形外科医に確認しました)
以上の理由から、当院ではPdWI(プロトン密度強調像)を撮像しています。
通常のPdWIではT2減衰の影響をなるべく避けたいので、TEを最短(10~20ms)に設定するのが望ましいですが、膝関節では軟骨と周辺組織のコントラストをつけたいので、TEを通常よりも少し長め(30ms程度)に設定しています。
PdWIなのでSNも良く、アーチファクトも比較的少ないので採用されています。
また、軟骨イメージングでは基本脂肪抑制を用いて、軟骨の信号を持ち上げて診断を行いますので、FS PdWIの撮像も行っています。
結局はDrの好みになりますので、一つの意見として聞いていただければと思います。

「MRCPで濃縮胆汁の時にはTEはどのくらいまで下げていますか?」
濃縮胆汁とは胆のうの炎症や閉塞などが原因で胆のう内の胆汁が凝縮されてしまう状態のことですね。
濃縮胆汁をいつものMRCPで撮像すると、胆のう・胆のう管が描出されないことによる胆石の描出不良や、外科の術中支援のための形態的構造の観察がしにくくなることが問題になります。
ではどのくらいTEを調節すればよいのか?というご質問の答えですが、当院では濃縮胆汁の所見があった場合には技師の判断でTE 400ms程度で息止め3D MRCP(FSE)を撮像しています。
(通常ルーチンは呼吸同期でTE 650ms程度)
TE400ms程度でも場合によってはまだまだ描出しにくいこともあります。
施設によってはTE300msの2D MRCPを追加したり、BalancedSSFPを利用した息止め3D MRCPを撮像したり、GRASE法(Philips)を利用した息止め3DMRCP(TE 100ms)を利用したりしているそうです。
濃縮胆汁の特徴は、T1WIで高信号・T2WIで高~等信号・MRCPで胆のうが見えない等なので、このような所見に気づいた際にはぜひ条件の検討をしてみると良いかもしれません。
濃縮胆汁とは胆のうの炎症や閉塞などが原因で胆のう内の胆汁が凝縮されてしまう状態のことですね。
濃縮胆汁をいつものMRCPで撮像すると、胆のう・胆のう管が描出されないことによる胆石の描出不良や、外科の術中支援のための形態的構造の観察がしにくくなることが問題になります。
ではどのくらいTEを調節すればよいのか?というご質問の答えですが、当院では濃縮胆汁の所見があった場合には技師の判断でTE 400ms程度で息止め3D MRCP(FSE)を撮像しています。
(通常ルーチンは呼吸同期でTE 650ms程度)
TE400ms程度でも場合によってはまだまだ描出しにくいこともあります。
施設によってはTE300msの2D MRCPを追加したり、BalancedSSFPを利用した息止め3D MRCPを撮像したり、GRASE法(Philips)を利用した息止め3DMRCP(TE 100ms)を利用したりしているそうです。
濃縮胆汁の特徴は、T1WIで高信号・T2WIで高~等信号・MRCPで胆のうが見えない等なので、このような所見に気づいた際にはぜひ条件の検討をしてみると良いかもしれません。

「試したことはないのですが、ターボファクター0での通常のSE法で身体を撮像した場合、T2WIで脂肪は低信号になるのでしょうか?」
ターボファクターとはFSE法におけるエコートレイン数(ETL)のことですね。また「ターボファクター0での通常のSE法」というのは、コンベンショナルSE法(CSE法)のことでしょうか。CSE法はあえて言うのであれば、ターボファクター(ETL)が「0」ではなく「1」になるかと思います。(ETLが0であれば、エコーを1つも収集していないことになってしまいます)
本題ですが、ETLが1であるCSE法でのT2WIは、恐ろしく時間がかかるので
(撮像時間=TR×NEX×位相エンコード数なので、例えば5000ms×2×256=42.7分!)
確かになかなか撮ることはありませんね。
脂肪のT2値は水ほど長くはなく、T2WIで脂肪が低信号に見える教科書も見受けられます。
FSE法では脂肪に対してMT効果が働かず、Jカップリングが作用しにくいため高信号となります。
このように脂肪信号に関しては、FSE法>SE法という特徴は大切なポイントですね。
ではどのくらい低信号になるのかに関しては、マルチスライスで撮るかシングルスライスで撮るかによってもMT効果の影響で変化するかもしれません。
実際に撮像した画像もあるのですが、ここではお見せしにくいので、今後の勉強会で詳しく取り上げられる機会がありましたら、是非実際の画像を一緒に見比べてみましょう!
ターボファクターとはFSE法におけるエコートレイン数(ETL)のことですね。また「ターボファクター0での通常のSE法」というのは、コンベンショナルSE法(CSE法)のことでしょうか。CSE法はあえて言うのであれば、ターボファクター(ETL)が「0」ではなく「1」になるかと思います。(ETLが0であれば、エコーを1つも収集していないことになってしまいます)
本題ですが、ETLが1であるCSE法でのT2WIは、恐ろしく時間がかかるので
(撮像時間=TR×NEX×位相エンコード数なので、例えば5000ms×2×256=42.7分!)
確かになかなか撮ることはありませんね。
脂肪のT2値は水ほど長くはなく、T2WIで脂肪が低信号に見える教科書も見受けられます。
FSE法では脂肪に対してMT効果が働かず、Jカップリングが作用しにくいため高信号となります。
このように脂肪信号に関しては、FSE法>SE法という特徴は大切なポイントですね。
ではどのくらい低信号になるのかに関しては、マルチスライスで撮るかシングルスライスで撮るかによってもMT効果の影響で変化するかもしれません。
実際に撮像した画像もあるのですが、ここではお見せしにくいので、今後の勉強会で詳しく取り上げられる機会がありましたら、是非実際の画像を一緒に見比べてみましょう!

